怒るのをやめると
- 心が穏やかに過ごすことができる
- 子どもがのびのびと行動できるようになる
- 怒らなくても子どもは成長することを理解できる
教育現場では、怒って指導をすることがとても多いように感じます。怒ることは確かに必要な場面があります。しかし多くのことで怒らなくても大丈夫です。怒ることで自分は感情的になり、周りが見えなくなります。また生徒は「恐怖」や「面倒くさい」と感じます。そして生徒の行動の目的が怒られないように行動することに変化してしまいます。これは教育としてはあまり良くありません。更に、先生の頭の中では「このことで怒ったから、次に誰かが同じことをしたら怒らなくてはいけない」という考えを持って指導をしていかなくてはいけなくなります。もし、同じ基準で指導ができなければ、生徒から「なぜ怒らないのですか?」と不信感を抱かれます。悪循環です。怒ることは、先生が短期間で生徒を思うように動かしたいという自己中心的な考えではないでしょうか?長期的な視点を持つと、話を聞いてあげ、生徒の考えを元にして対話していくことが大事ではないかと思います。「怒られない」と生徒が感じ、心理的に安全だと思えばのびのびと自分で考えて行動してくれます。時には失敗することもありますがその時は対話すれば大丈夫。ちゃんとわかってくれます。そして先生側が考えもしない素晴らしい行動をしてくれるときがあります。それが生徒の自信となり子どもたちがどんどん成長していきます。ぜひそれを感じてみませんか?
私は以前は怒って指導することが当たり前でした。そのような指導法になったのは、周りの先生がそのようにしていたからです。特に学校で力がある先生ほど威圧的で怒って指導をするような傾向がありました。その指導に少し憧れを持っていたように思います。私は真似をしながら、どのように怒ったら生徒がビシッとして行動するようになるかを考えながら教師として取り組んでいきました。しかし、いつも私の中にはモヤモヤが溜まっていました。「どの基準で怒ればいいのか」「自分の雰囲気で怖いと思われるようにしなくては」など色々と無駄なことをたくさん考えながら、そして生徒たちと色々と駆け引きをしなくてはなりませんでした。そのため生徒とは良い関係が築けていたとは言い難く、とても嫌な毎日を過ごしていました。でもこれが「良い先生になるための方法」だと思い込んでいたので取り組んでいきました。
ここで私の中で変わるキッカケが2つ起きました。1つは東京医療保健大学の女子バスケットボール部監督をされている恩塚亨の影響です。「ワクワクが最強」というワードに魅了されました。行動を起こす理由を「怒られないように」という消極的なことではなく、「楽しい、やってみたい」という積極的なことに変化させ、子どもたちの成長をサポートしたいと心から思いました。もう1つは特別支援学級に異動になったことです。特別支援学級は様々な苦手を抱えた子どもたちが在籍しています。周りの子どもよりも苦手が多いため、失敗もたくさんたり、周りから不当な扱いを受けているような子どもとたくさん出会いました。そんな子どもたちに対して怒って指導しても全く意味がないと感じました。そのため毎日コツコツと対話しながら、失敗や挑戦を通して苦手の克服に取り組んでいました。その過程では、子どもの意思をしっかりと尊重しながら取り組みました。例えば、「嫌だ」と言っていることに対しては無理やりするようなことはせず、本人の気持ちが準備できるまで待ちました。感情が高ぶり、暴力的な行動に出る子どももいましたが、教師側が落ち着いて対話し、気持ちを受け入れてあげながら関わっていきました。
この2つのキッカケから私の教師人生から「怒る」ということがほぼなくなりました。すると、私の中のもやもやした気持ちもなくなり、怒らない指導が私自身にマッチしていると強く感じました。実際、怒らないで指導していくと子どもたちが楽しそうに、でも一生懸命に取り組むことが多くなります。ただし、教師側の工夫が必要ではあります。ある日の部活動で連絡無しで集合時間に遅れてきた生徒がいました。理由を聞くと、「寝坊しました」と言いました。こんな生徒にどのように対応されますか?以前の私なら、怒鳴ってから罰として掃除をさせていたと思います。しかし、そのときは「わかった、次からは気をつけよう。ただ、できれば連絡をしてほしい。先生としては心配するから。よろしく!」というような感じで対応しました。それからも遅れることは時々ありましたが、連絡を入れてくれることがほとんどでした。遅れてきた時点で、誰もが申し訳ない気持ちで心がいっぱいになり、次から気をつけようと思っているはずです。だから、子どもは自分で行動の改善に取り組みます。さらに、その先に待っている活動がワクワクするものであるならば、より頑張ろうとします。その他のことでも口出しする機会を減らしていきました。先生は何かと教えたくなるものだと思います。私も色々と指示を出したり、細かく教えたいと感じていましたが、子どもたちが自分たちで主体的にやろうと思っているときには子どもたちに考えさせ、質問されたら答えるくらいのスタンスでいいのかなと感じます。自己満足が大切なのではなく、1番の目的は子どもの成長だと捉えています。まだまだ私自身の学ばなければいけないことがたくさんあるので、子どもの成長のためには何が有効なのかを学び続けてたいと思います。
これを読んでくださった方々、ぜひ怒る指導をやめてみませんか?怒る気持ちの裏側に、子どもを思い通りに動かしたいという気持ちがありませんか?子どもも1人の人間です。対話しながら、成長を見守っていきませんか?そうすることで自分自身もきっと穏やかな気持で過ごせるようになります。試してみてください。

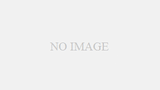
コメント